2015年2月3日(火) 22:30
TUIの棲家1

written by hom [TUIの棲家] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
- この記事へのトラックバックPingURL
2015年2月3日(火) 22:23
こどもと暮らす、こどもと遊ぶ、愉しい家1
これからこちらでもご報告^^

written by hom [こどもと暮らす、こどもと遊ぶ、愉しい家] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
- この記事へのトラックバックPingURL
2015年2月3日(火) 17:24
朝陽のあたる家
ボブ・ディランやアニマルズが歌いスタンダードナンバーになっています。
旋律が綺麗ながらも、なんとも物悲しく感じられる、一度聴いたら忘れられない名曲です。日本では浅川マキやちあきなおみがカバーしています。
タイトルから受けるイメージとは裏腹に、歌詞の内容は、娼婦に身を落とした女性が半生を懺悔する歌なのです。
物悲しく感じられる理由は、そうした暗い情念に満ちた内容だからです。
その曲も好きなのですが、もっと大好きなのがホンモノの「朝陽の当たる家」

住宅を設計する時、どんな敷地条件であろうとも何とかしてあらゆる手段を駆使して、太陽の陽ざしを取り込む努力、工夫をします。
その陽ざしの中でも朝陽は特に大事にしたいと思っています。
朝一番の新鮮な陽ざし、元気出ますよね^^
ちなみに僕の家、北東角にある普段は陽のあたらない暗くて寒い階段室。
冬の朝陽の角度に合わせ窓の内側を斜めにカットして、少しでも中で光が広がる工夫を・・・ほんの数十分のことですが、寒い朝の活力になってます。
written by hom [考・想・感] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
- この記事へのトラックバックPingURL
2015年1月1日(木) 00:00
謹賀新年2015
今年もたくさんのお施主さんに幸せと元気を届けます!(もしかして逆!?)
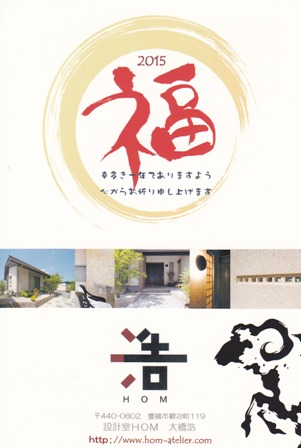
引き続き、よろしくお願いします!
written by hom [日常] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
- この記事へのトラックバックPingURL
2014年11月24日(月) 23:01
そうだ、豊橋へ行こう!
written by hom [放浪] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
- この記事へのトラックバックPingURL
2014年11月13日(木) 23:56
能楽らいぶ
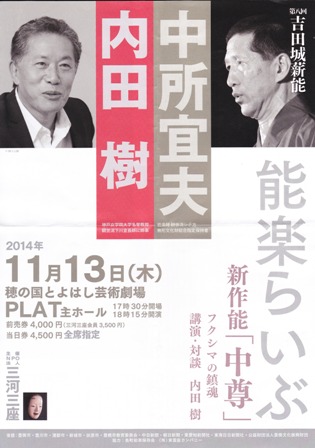
能楽にしっかりと触れたのは始めての経験でした。
感想は・・ワカラナイ・・でした。
けれども、です。
第2部の講演会(講師:哲学者、武道家 内田樹氏)を聴いて一気に「能をやってみようかな・・」というところまで引き込まれました。
それほどわかりやすく楽しい口調そして内容でした。
*能楽の魅力は、そもそも見て聴いて訳わからないところ。
*独特な身体の動きである”摺り足”は、自分から能動的に動くものではなく、見えない大きな力で前面から受動的に引っ張られる感覚でないと表現できない。
*両腕を広げる所作は、身体全体を覆うゼリー状の塊の中を浮遊する感じ。
etc.etc.
というような、自ら能をされる方ならではの技法の解説から、中世(平安末期~鎌倉・室町)日本人が、どのような言葉で、どのような所作で、何を考えて生きていたのか?・・それをわかりたくて能を始めた、という興味深いエピソードまで、一つ一つの言葉に引き込まれました。
そしてその哲学的な解釈には日本人として納得できる気がします。
”自然と人間の境界には「壁」とか「門」とか「石」とか堅牢なバリヤーが置かれるのが普通です。「何か」が人間の世界に入り込まないように、人間が道に迷ってうっかり「向こう側」に踏み入らないように境界線を管理するのです。でも中世日本人はそこに無生物ではなく、よく整えられた生身の身体を置くという手立てを思いつきました。整えられた身体は野生と人間を媒介し、架橋することができる。これはおそらく日本列島に独特の発想だと思います。そしてそこから「修行」という方法、「道」という概念が生まれてきた。”
難しいけれど何となく腑に落ちる、という気がしませんか?^^
written by hom [日常] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
- この記事へのトラックバックPingURL
2014年11月12日(水) 23:55
熱海湯階段
今回のメインイベントは、ビッグサイトで開催されたジャパンホーム&ビルディングショー、の中で行われたセミナーへ。
お題は”住宅設計者の現在と未来”。
その題目(もちろん講演者も、ですが)に惹かれました。
現在の目の前の仕事で飽和状態になっている自分に、「そうか、自分にはまだ未来があるんだっ!」と気付かされ
何かパワーを貰えるのでは、という思いきり他力本願な動機付け。
それでもやはり、時代の先頭に立って物事を動かしている方たちの言葉には力がありました。
この情報あふれる現代、豊橋の事務所内で自分なりに数多のメディアの中から取捨選択し、業務上の糧や知識を得ているつもりではいます。
しかし、こうして自分の足で、カラダを動かし、同じ志を持った(たぶん)大勢の方たち(皆さん目つきが真剣です)の中のひとりとして、第一線で活躍されている方の生の声を拝聴すると、
いかに自分が井の中の蛙か、ぬるま湯に浸かっているかが身にしみてわかりますし、同時に本当にいい意味で刺激になります。
続けねばっ!です。
という大義名分の下、第2の(第1の!?)目的である東京放浪の始まりです^^
今日は3時間ほどのミニ放浪。
まずは神楽坂にOPENしたla Kagu(隈研吾氏デザイン監修)へ。
新潮社の書籍倉庫だった古いスレート葺きの建物を、その古いまま使ったリノベーション。地形を活かしたアプローチのウッドデッキが圧巻です。
立地、設計者、オーナー(新潮社)、運営者(サザビーリーグ)、カフェ、生活雑貨、ブックディレクターのいる本屋、働くスタッフたち・・・
どれをとってもまさに、THE東京!でした。
その後は神楽坂の賑やかな商店街から一本入った谷道の抜け道、階段路地を満喫して終了でした。
熱海湯銭湯横の脇道であることから名付けられた”熱海湯階段”
都会のど真ん中でありながらの、その狭さと苔むした階段が素敵です。
written by hom [放浪] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
- この記事へのトラックバックPingURL
2014年9月2日(火) 13:43
加賀百万石2014
何故 金沢?
僕が勝手に師匠と仰ぐ建築家<”勝手師匠”と呼ばせていただいています^^>のひとり、中村好文氏の展覧会が8月末まで金沢21世紀美術館で開催されている、というのが大きな動機付けでした。
金沢21世紀美術館は機会あれば行きたい、と思っていたので、これこそ一石二鳥、一挙両得、棚からぼたもち(ちょっと違うか!?)、ということで、新幹線米原経由、北陸本線特急しらさぎでいざ、金沢へ!
出迎えてくれたのは、アルミトラスの『もてなしドーム』と、『鼓門』。
鼓の調べ緒をモチーフにした赤門をシンボルにしたこのプロジェクト、
工期7年!総工費172億!金沢の顔として十分風格があります。
加賀藩前田家は江戸時代約290年間を通して徳川幕府に謀反の意がないことを示すために、ことさら武の印象を抑え、学問や美術、工芸、芸能を奨励し、その発展に尽くしたそうです。
そしてその後それに加え、戦災を受けなかったこともあり、当時のまちなみ、芸能、工芸、食などの文化も現在に至るまで綿々と受け継がれています。
そうした伝統を踏まえた落ち着きと風情を兼ね備えた素敵な街でした。
そしてそこに新しい文化的なものを取り入れる度量、感性などのバランス感覚にも感動です。今もなお、伝統を作り続けています。
その新しいものの代表格、金沢21世紀美術館。
金沢のあの場所の歴史、地勢的な潜在力を見事に読み取り、そしてカタチにした設計者の力量に感服です。
美術館建築の固定観念である重厚感を消し去った、あくまで軽く、シンプルにOPENな、という明快なコンセプトは、そこに集う人たちの数や表情を見ると、充分すぎるほど受け入れられているように感じました。
もうひとつ、静寂、気品、風格、荘厳etc..その文字そのままの佇まいを見せる
鈴木大拙記念館へ。
この建物の設計者谷口吉生氏も僕の”勝手師匠”のひとり。
いつものことながらその緊張感に打ちのめされます。
仏教哲学者鈴木大拙にちなみ、来館者自ら思索できる「思索空間棟」の周りを取り囲む「水鏡の庭」
ここにたどり着いた瞬間、息を呑み、背筋が伸び、そして心が洗われる感覚に陥ります。
美しい建築にはひとの心を動かす力があります。
その他金沢うんちく...いろいろ凄いです。
伝統という土壌があってこそ発信できる文化なんでしょうね。
*世界で最も美しい駅14駅のひとつ。
*世界で最も素晴らしい駅ベスト10。
*都市照明の国際コンペ「シティ・ピープル・ライト・アワード」第3位。
written by hom [放浪] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
- この記事へのトラックバックPingURL
2014年8月1日(金) 16:03
請負~請け負け!?
本屋でブラブラしててタイトルに惹かれて手に取った本です。
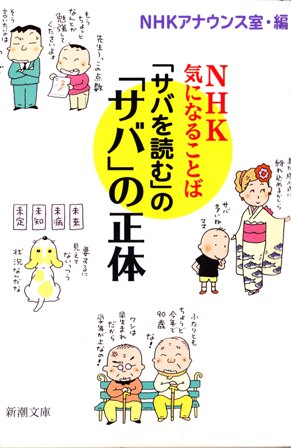
元々雑学本は好きな方ですが、この本は特化して面白かったです。
何気なしに普段使っていることばたちの意味・由来・正しい使い方を、
NHKとしての見解を含めながら解説している内容なんですが、
それぞれのことばの、いかにも興味をそそるサブタイトルの付け方、文章の
平易さ、小気味良いテンポ、かつポイントをついた明快さ、などが相まって一気に読めます。
「へぇー」、「なるほどねー」の連続。
改めて日本語の面白さ、奥深さを堪能しました。
その中で、建築業界につながることばがあり、思わず、これだよっ!
ってひざを叩いたことをご紹介^^
【値段を安くするとなぜ「勉強」?】という一文からの抜粋です。
そもそも古代中国での「勉強」の意味は、その漢字の通り”強いて勉める””無理強いをする””広く努力する”の意味で使われていました。
そこから”お客のために少し無理をして利益を薄くして売る”という意味合いで使われていると言うことです。
その値段を安くすることをおまけする、といいますよね。これは漢字で「御負」。
この”負”は、お客の意見を取り入れてお客との取引に”負ける”からきているようです。
その「負け」とは何か?
設計が完了し、工務店さんの見積り金額が双方合意に至ればそこで”請負”契約を締結します。
そして工事が始まりその途中段階で、図面に記載が無かったり、または図面通り出来上がったことでもお客さんの気が変わったり、イメージが違ったり、と言う感じで追加工事や手直し工事が発生する場面がよくあります。
そんな時全てではありませんが、設計監理側の判断として工務店さん側にその追加or手直し工事費用をお願いする場合があります。
その時工務店さん側からたまに出る言葉なんですが、
「しょうがないですねー、私らは請負(請け負け)なので・・・」
とちょっと皮肉を込めて返されることがあります。
そんな時感じる違和感はいったいなんだろう?といつも思っていました。
あなたたちは負け組なのか・・・?
そーなんです、考え方が違うんです、しょうがない、ではないんです。
「勉強」「御負(おまけ)」と同じ勝ち負けではなく、お客さんのために少しだけ無理をして、
お客さんに一歩譲る感覚の「負」なんです!
あー、すっきりした。これからはそう切り返そうと思います。
そう思うことが潤滑油になり、双方物理的にも心理的にもプラスになると思いませんか?
そもそもお客様は神様^^ですし。
追記;アンタはイイよね、自分のフトコロ痛まないから・・なんて言われそうですが、もちろんすべて工務店さんに一方的に押し付ける訳ではなく、お客さん了解のもと、質を落とさず他の部分を変更したり、完成した工事部分が計らずも見積金額より安くできた項目をCHECKして、その金額を相殺する、といった調整も監理業務の重要な仕事です。
written by hom [日常] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
- この記事へのトラックバックPingURL
2014年6月16日(月) 21:26
営業Ⅱ
まずはひとつひとつの目の前の仕事を誠意と熱意を持って取り組むこと。
その信念を持ち、開設26年目を疾走(迷走!?)しています。
とは言いながらも、活字の印刷物になるような営業活動も機会を探って登場しています。
そんな中、毎年この時期の恒例広告掲載^^
豊橋落語天狗連さんの小市民寄席パンフレット、もう15年も連続で載せていただいています。
天狗連さんが考えてくれるユーモアセンスがキラリと光るひと言付の小コマ、
いつもお世話になっている神野臨海さんのコマとともに過去5年間切り抜きご紹介です。






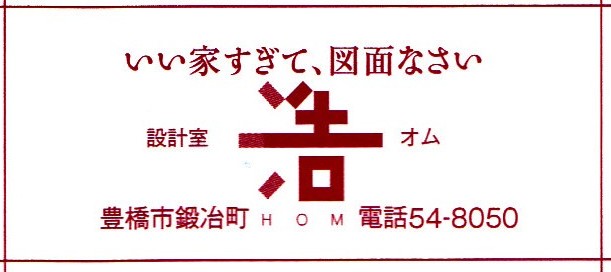



楽しいですよね!
その前10年間分、ご興味のある方はこちら(2009/10/03ブログ”営業”)
written by hom [考・想・感] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(0)] [TB(0)]
- この記事へのトラックバックPingURL